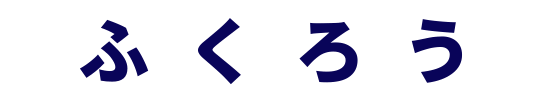本サイトは、以下の手順で、衆議院の現職273人を掲載しています。
- 議員1人1人の質疑を分析
- 現職を経済政策で分類する
- 投票の判断材料を提供
以下、順番に説明します。
1.議員1人1人の質疑を分析
衆議院の現職は、国会の予算委員会や各省庁の委員会で質疑を行っています。
例として、2人の質疑を見ていきます。
例1 河野太郎の質疑 @外務委員会
消費税20から26%というのは、これは純粋に今の財政を均衡させるために…消費税の税率のみで調整をしようとした場合…単純に、数理的に計算をしただけでございます…
第198回国会 衆議院 外務委員会 平成31年4月17日
河野議員は、消費税を20%以上に引き上げるような議論を行っています。
例2 玉木雄一郎の質疑 @予算委員会
私は、やはり消費税の減税も一つの政策手段として考えるべきだと思います。
第201回国会 衆議院 予算委員会 令和2年6月10日
玉木議員は、消費税の減税を訴えています。
このように本サイトでは、国会会議録検索システムに保管されている膨大な議事録から、消費税の減税に賛成・反対した議員を見つけ出し、その質疑とリンクを掲載しています※1。
2.現職を経済政策で分類する
次に、2人を以下のように分類しています。
- 河野太郎以外に投票する
- 玉木雄一郎投票候補
分類の基準は、消費税の減税を含む、以下4つの経済政策です※2。
上記4つのいずれかに反対した議員を以外に投票する、賛成した議員を投票候補に分類しています※3。例として、以下8人ほど列挙します。
河野太郎 以外に投票する(消費減税に反対)
玉木雄一郎投票候補 (消費減税に賛成)
野田佳彦 以外に投票する(財政出動に反対)
高市早苗 投票候補 (財政出動に賛成)
山下貴司 以外に投票する(移民規制に反対)
石川香織 投票候補 (反自由貿易に賛成)
藤田文武 以外に投票する(解雇規制に反対)
森山浩行 投票候補 (国営化に賛成)
こうした分類の積み上げにより、2月26日時点で現職273人の掲載が完了しています。次の衆院選まで分類作業を行い、掲載人数を増やしていきます。
3.投票の判断材料
衆院選では2枚の投票用紙を記入します。
- 1枚目 候補者の氏名
- 2枚目 政党名
本サイトでは、分類した議員を集計し、投票判断における消去法の順位を割り出しています。以下、投票用紙1枚目、2枚目の順番に説明します。
1枚目の投票用紙「候補者の氏名」
1枚目の投票用紙は、選挙区ごとに集計されます。
以下、3つの選挙区を例にとります。
例1 神奈川15区
神奈川15区の現職は、以外に投票する議員が1人しかいません。
| 当選者と次点 | 得票率 |
|---|---|
| 河野 太郎(当選) | 55.6%(128,881票) |
| 佐々木 克己 (落選) | 17.2%(39,980票) |
神奈川15区では、河野太郎以外に投票する判断になります。衆議院では神奈川15区のような選挙区が多く、消去法で選ぶことがカギになってきます。
例2 香川2区
香川2区の現職は、以外に投票する議員、投票候補の議員が1人ずついます。
| 当選者と次点 | 得票率 |
|---|---|
| 玉木 雄一郎(当選) | 66.4% (89,899票) |
| 瀬戸 隆一 (自民、比例当選) | 28.8% (39,006票) |
玉木議員のほかに、瀬戸議員を以外に投票する議員として分類・掲載しています。香川2区での消去法の順番は、瀬戸>玉木になります。
例3 東京19区
東京19区の現職は、以外に投票する議員が2人います。
| 当選者と次点 | 得票率 |
|---|---|
| 末松 義規 (立民、当選) | 39.4% (76,899票) |
| 松本 洋平(自民、比例当選) | 38.2% (74,435票) |
2人とも財政出動に反対しているため、以外に投票する議員として分類・掲載しています。東京19区では、末松・松本以外の候補者を検討することになります。
2枚目の投票用紙「政党名」
2枚目の投票用紙は、選挙ブロックごとに集計しています。
以下、2024衆院選の中国ブロックを例にとります。
例 2024衆院選の中国ブロック
まず「以外に投票する」現職の人数を、政党ごとに集計します(X)。次に、それを出馬する現職の人数 (G) で割ります。
| 政党名 | X. 以外に投票 | G. 出馬する現職 | X ÷ G |
|---|---|---|---|
| 維新 | 1人 | 1人 | 100% |
| 自民 | 14人 | 18人 | 78% |
| 中道 | 4人 | 3人 | 67% |
この割合(X ÷ G)が高い順に、各政党を左から並べます。
70% > 67% > 50%
「以外に投票する」現職÷ 出馬する全現職
この順位を念頭に置きつつ、議席数が0の政党と比較検討することになります。以下、2026衆院選の政党の消去法順位になります。
北海道 中道 > 自民
東北 自民 > 中道 > れいわ
北陸 自民 > 中道
東京 自民 > 維新 > 中道 > れいわ・参政・共産
南関東 維新 > 自民 > 中道
北関東 自民 > 中道 > 国民民主 > 共産・れいわ
東海 維新 > 自民 > 中道 > 国民 > れいわ・共産
近畿 維新 > 自民 > 中道 > れいわ・共産・国民民主
中国 維新 > 自民 > 中道
四国 自民 > 中道 > 国民民主
九州 中道 > 国民 > 自民 > 減税ゆうこく・れいわ・共産
全11選挙ブロックの小選挙区、比例重複、比例単独の候補者の分類が完了しました(2026年1月27日)。
まとめ
本サイトを要約すると、次のようになります。
- 現職の候補者と既存の政党を、消去法で順位付けしている
この順位をにらみつつ、新規の候補者と政党を比較検討することになります。
※1 本サイトが対象とする議論は、国会議員としての仕事、すなわち、委員会質疑のみです。例えば、国会以外の場で積極財政を語っていても、国会では全く質疑をしない議員(例えば、小沢一郎)もいます。そのような議員は掲載していません。
※2 例えば、共産党の田村議員は、1.消費税の減税には賛成していますが、2.財政出動には反対しています。この場合、数字の小さい政策を優先して投票候補に分類しています。このような議員には注意マークをつけています。
※3 議員の分類が途中で変更される可能性があることを予めご了承ください。例えば、元々緊縮財政派だったが、途中から積極財政派に転向した議員として、松原仁議員がいます。それに応じて本サイトの方でも、分類を変更しています。変更があった時は、お知らせ欄に告知しています。
※4 現職の質疑が誤っている原因は、日本経済を正しく認識していないことによるものがほとんどです。例えば、「日本経済は堅調に推移」「ハイパーインフレーションが近い」「日本は放漫財政」のような決まり文句を繰り返していますが、これらは事実に反しています。その事実を示すために、以下のグラフを作成・活用しています。